皆さんこんにちは
花を買う人(はなを)です。
毎年朝顔を育てているのですが、ツルの力強さに驚かさせます。支柱へツルを絡ませて、支柱もたりなくなると今度は絡まれるすべての物に絡まっていくのです。そんなツルを見て「なんで目の見えない植物が、柱を見つけてツルを絡ませることができるのか?」と疑問に思ったことは無いでしょうか。ということで今回は、ツル植物が近くの柱やモノに絡みつく理由と、その原理について解説します。
なぜツル植物は絡みつくのか?

ツル植物がモノに絡みつく最大の理由は、生き残るためです。
アサガオのようなツル性の植物は、丈夫な幹を発達させて自立する代わりに、細長い茎(ツル)や巻きひげを使って他の植物や支柱に巻き付き、よじ登りながら成長します。彼らにとって、茎だけで自立するのは難しいため、サポートが必要です。
競争の激しい自然界において、他の植物よりも高い位置で光を遮られずに葉を展開することは、エネルギー源である光合成を最大限に行うために極めて重要です。この「登攀(とうはん)」という運動成長は、ツル植物にとって生存に不可欠な形態形成反応なのです。
絡みつく原理
ツル植物がモノを見つけ、実際に絡みつくまでの動きには、二つの重要な原理が働いています。
支柱を探す「回旋運動」
ツル植物の先端は、単にまっすぐ伸びるだけでなく、常に回転しながら伸長する「回旋運動」を行っています。これは、周囲に支えとなるものがないか探るための行動です。
この回旋運動には、植物が重力(下方向)を感知して上へ伸びようとする性質、すなわち重力屈性が深く関わっていることが、1880年にはすでにダーウィン父子によって指摘されていました。

【重力センサーの役割】 アサガオの実験から、重力を感知するために必要な「重力感受細胞」が、ツル植物のよじ登りの原動力である回旋運動に必須であることが明らかになっています。もしこの重力感受細胞が正常に働かない変異体(例:枝垂れアサガオ)では、回旋運動や重力屈性ができなくなり、その結果、支柱に絡みつけず枝垂れてしまいます。
接触すると曲がる「接触屈性」

ツルの先端が探し回っている時に、支柱やモノに接触(物理的な刺激)すると、それが引き金となって巻き付きが始まります。この、接触刺激に反応して一定の方向に動いたり成長したりする性質を接触屈性(Thigmotropism)と呼びます。
ツルが曲がる仕組み
ツルや巻きひげがモノに触れると、その刺激は細胞に伝わります。触れた側の細胞は伸びるのを止めます。触れていない反対側の細胞は、より早く伸びるように促されます。この伸びの差によって、ツル全体が接触したモノの方へ急速に曲がり、巻き付いていくのです。
この現象は、植物ホルモンの一種であるオーキシンが、触れていない側の細胞へ輸送され、その細胞の成長を促進することで引き起こされると考えられています。
まとめ
いかがでしたでしょうか。今回はツル植物のツルが伸びる理由と仕組みについて解説しました。ツル植物の登はん戦略は、重力感知による「回旋運動」と接触刺激による「接触屈性」という高性能なメカニズムによって、彼らが進化の競争を生き抜くための鍵となっていることがわかりました。
私のサイトでは花にまつわる雑学を紹介しています。面白そうだ!と思って下さった方、是非SNSのチェックよろしくお願いします。
・X
・インスタ
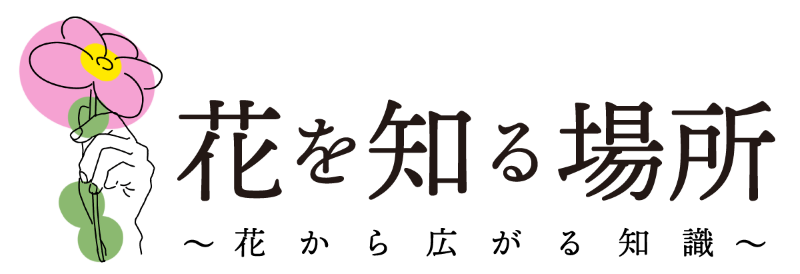


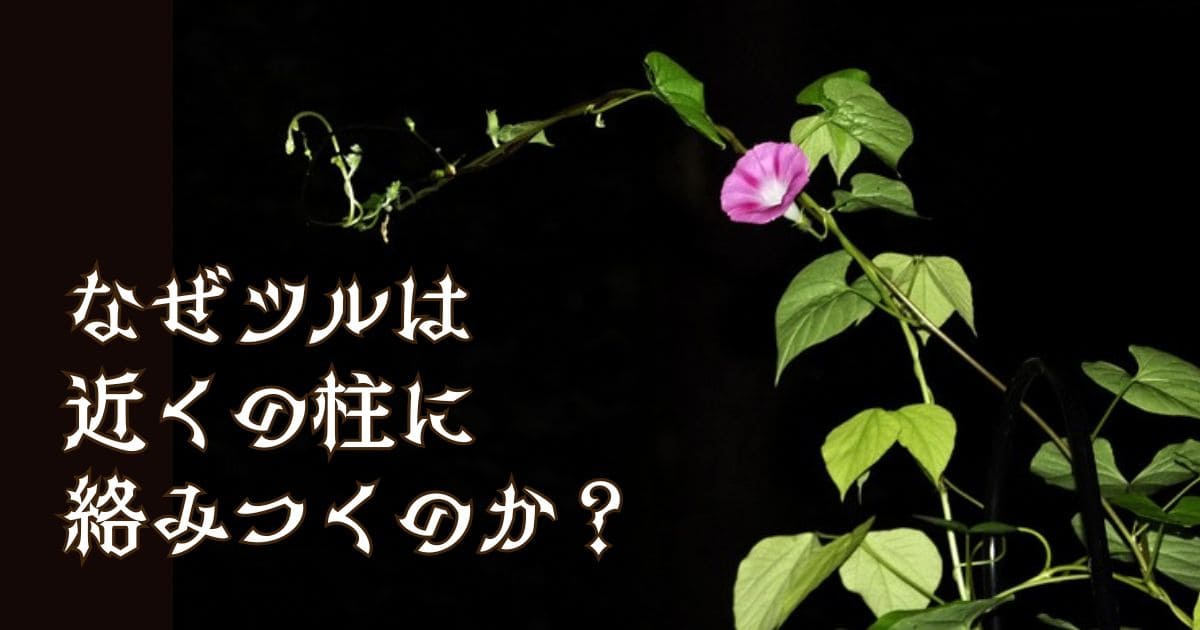


コメント