皆さんこんにちは
花を買う人(はなを)です。
秋の山々を赤や黄色に染め上げる紅葉は、私たち日本人にとって特別な風景です。この美しい季節の主役といえば、「カエデ」と「モミジ」。普段、何気なく使っているこの二つの名前ですが、実はとても複雑で興味深い関係があるのです。
どいうことで今回は、「カエデ」と「モミジ」の違い、関係性について説明します。
一見そっくり?「カエデ」と「モミジ」の分類学的な真実
そっくりなカエデとモミジ、結論から言うと植物学的にはすべて「カエデ」の仲間です!
カエデもモミジも「カエデ属」という大きなグループに分類されます。このカエデ属は、ムクロジ科に属する落葉高木の総称です。

例えるなら、「カエデ属」という大な傘があり、その傘の下に「○○カエデ」や「○○モミジ」といった様々な品種が並んでいるイメージです。
英語圏では、このカエデ属の植物はすべて「Maple(メープル)」と呼ばれています。私たちが親しんでいる「モミジ」は、特に美しい日本のカエデということで「Japanese maple(日本のカエデ)」と表現されることが多いです。
名前に込められた意味の違い
カエデとモミジが同じ植物の仲間であるにもかかわらず、なぜ二つの名前があるのでしょうか。その答えは、遥か昔の日本語の歴史の中にあります。
「カエデ」は「カエルの手」から

「カエデ」という名前は、その葉の形に由来しています。カエデの葉は手のひらのように切れ込みが入っていて、これがカエルの手(蛙手:かへるで)に似ていたことから、「カへるで」と呼ばれ、それが時代とともに変化して「カエデ」になったとされています。
日本最古の歌集である『万葉集』には、既に「かへる手」という表記でカエデが登場する和歌が詠まれています。
わが宿に 黄葉 ( もみ ) つかへる手見るごとに 妹をかけつつ恋ひぬ日はなし
「モミジ」は「色づくこと」そのもの

一方、「モミジ」という言葉は、もともと特定の植物の名前ではありませんでした。
「モミジ」の語源は、古い日本語の動詞「もみづ」(清音「つ」)です。この「もみづ」は、冬が近づき、植物の葉が赤や黄色に変色する現象そのものを指していました。また、反物(着物の生地)を植物の色素で染め、揉み出して水中に色が染み出す様子も「もみづ」と表現されていたそうです。
この「もみづ」という動詞の連用形(もみぢ)が次第に名詞として使われるようになり、特に紅葉が格別に美しいカエデの仲間を指して「モミジ(紅葉)」と呼ぶようになりました。その代表的な品種が、カエデ科カエデ属のイロハモミジです。
日本独自の文化が生んだ「見分け方」のルール
植物学的には同じカエデ属でも、日本では見た目によって「モミジ」と「カエデ」を呼び分ける独自の文化が発展しました。私たちが日常で「カエデ」と「モミジ」を見分けるときの簡単なルールは、葉の切れ込みの深さです。
○○モミジ
葉の切れ込みが深く、手のひらの指のように分かれている品種。大きな切れ込みが5つ以上あるものがモミジと呼ばれることもあります。
○○カエデ
葉の切れ込みが比較的浅い品種。
ただし、この分け方も絶対的ではありません。秋になって赤く色づいた木であれば、葉の切れ込みが浅い〇〇カエデであっても、「赤く染まったもみじがキレイ」と言っても間違いではありません。本来、「もみじ」は紅葉した樹木の総称という意味も持っているからです。
カナダの国旗とメープルシロップ

カエデは日本だけでなく、世界中で愛されている植物です。カナダの国旗に描かれているのは、北米原産のサトウカエデの葉がモチーフです。サトウカエデの樹液は糖度が高く、これを煮詰めて作るのが、おなじみのメープルシロップです。日本でも、イタヤカエデやウリハダカエデの樹液を使ってメープルシロップを作ることができますが、日本のカエデの樹液の糖度は、サトウカエデの約半分程度だそうです。
まとめ
いかがでしたでしょうか。今回は紅葉の仕組みについて解説しました。「カエデ」と「モミジ」は、植物学上はすべて同じ「カエデ属」に分類される植物であり、私たちが普段使っている二つの名称は、日本の長い歴史と文化の中で生まれた独自の呼び分けであることがわかりましたね。知識を持って紅葉の風景を味わうことで、今年の秋の楽しみかたは格段に深まるでしょう。
私のサイトでは花にまつわる雑学を紹介しています。面白そうだ!と思って下さった方、是非SNSのチェックよろしくお願いします。
・X
・インスタ
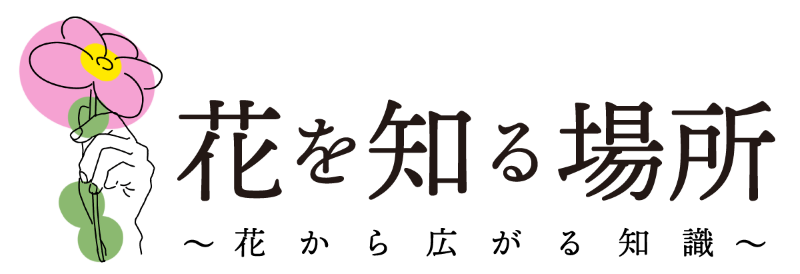








コメント